遺品整理士の資格は、合格率65%前後と比較的取得しやすく、通信講座やレポート提出を中心に進められるため、誰でも挑戦しやすい資格です。必要な知識は法制度やマナー、実務に関する基本的なもので、計画的に学べば短期間での取得も可能。今回は、資格の概要から難易度、合格のための勉強法まで徹底解説します。
遺品整理士の資格難易度は低め!合格率65%で誰でも狙える理由

遺品整理士の資格は、国家資格ではなく民間資格であり、試験形式は通信講座を受講し、課題レポートを提出する方式です。一般的な筆記試験や口頭試験がなく、自宅で学習を進められるため、忙しい社会人や主婦の方でも取り組みやすいのが特徴です。
合格率は公式発表で約65%前後。つまり3人に2人が合格できる水準で、しっかり教材を読み込み、レポートを丁寧に作成すれば十分に合格が狙えます。
この資格の目的は、遺品整理業務の質を向上させるための基礎知識と倫理観を身につけること。そのため、難易度を極端に高くするよりも、一定の知識を確実に理解させることが重視されています。
また、学習範囲は法律や廃棄物処理、供養、相続に関する基本知識と、現場対応のマナー・作法が中心です。専門的な法律資格のように難解な判例を暗記する必要はなく、テキストと課題を地道にこなせば合格できます。
取得後は、遺品整理業者としての信頼性向上や、顧客からの安心感獲得につながるため、業界での評価も高いです。結果として「資格の価値は高いが、取得の難易度は低め」というバランスの良い資格と言えるでしょう。
遺品整理士資格とは?取得するメリットと業界での評価

遺品整理士資格は、一般社団法人「遺品整理士認定協会」が認定する民間資格で、遺品整理業務に関する専門知識と倫理観を証明するものです。遺品整理は単なる片付け作業ではなく、故人や遺族の気持ちに寄り添いながら、法律やマナーに基づいて品物を整理・処分する必要があります。そのため、正しい知識と対応力を備えた人材を育成する目的で、この資格制度が作られました。
資格取得のメリットは多岐にわたります。まず、業務の信頼性向上です。遺品整理は、遺族の大切な思い出や財産に関わるため、依頼者は信頼できる業者を選びたいと考えます。資格保有者であることは、業務品質の保証となり、顧客の安心感につながります。次に、競合との差別化です。同業他社が乱立する中で「資格保有者在籍」という肩書きは、集客や契約獲得において強力な武器になります。
また、遺品整理業は今後も需要が高まる分野です。高齢化が進む日本では、遺品整理や生前整理の依頼件数は増加傾向にあります。そのため、資格を持つことで長期的な仕事の安定性やキャリアアップの可能性も高まります。特に行政からの委託業務や、不動産・葬儀関連業者との連携においても、資格は大きな評価ポイントとなります。
資格取得の流れと必要条件

遺品整理士資格の取得は、専門学校や通学講座ではなく、基本的に通信教育で完結します。申し込みから認定までの流れは比較的シンプルで、社会人や副業として資格取得を目指す人にも取り組みやすいのが特徴です。
取得の一般的な流れは以下の通りです。
申し込み後、遺品整理業務に関する法律、マナー、廃棄物処理法、遺族対応の方法などをまとめたテキストが届きます。学習期間はおよそ2ヵ月を目安としており、自分のペースで進められます。
学習後、課題レポート(複数問)を作成して郵送またはwebにて提出します。このレポートは記述式が中心で、テキストを参照しながら回答可能です。
レポートの審査に合格すると、晴れて「遺品整理士」の資格が授与されます。合格率は約65%前後とされ、努力すれば十分取得可能な水準です。
必要条件としては、年齢や学歴に制限はなく、誰でも受講可能です。未経験者でも挑戦できるため、異業種からの参入や副業として資格を活かす人も多いです。
このシンプルな流れと受験ハードルの低さが、遺品整理士資格の人気の理由の一つとなっています。
試験内容と出題傾向

遺品整理士資格の試験は、一般的な国家試験のような会場試験ではなく、通信教育課程の課題レポート提出が評価の中心です。そのため、テキストの内容をしっかり理解していれば、合格は十分可能です。
出題範囲は以下のような内容を理解しているかを問われます。
- 遺品整理の基礎知識
遺品整理の目的や流れ、必要な事前準備、作業工程など。 - 関係法令
廃棄物処理法、遺失物法、古物営業法、個人情報保護法など、業務に関係する法律。 - 遺族対応・マナー
遺族とのコミュニケーション方法、心理的配慮、適切な言葉遣い。 - 特殊清掃・現場安全管理
孤独死や事故現場など、特殊な環境での安全対策と清掃方法。 - 再利用・リサイクルの知識
資源の分別、再販売、寄付などの選別方法。
レポートは記述式で、テキストを参照しながら回答できるため、暗記よりも理解と文章力が重視されます。
合格のコツは、
- テキストを全範囲通読する
- 実務例や法律の根拠を意識して覚える
- 過去の事例やトラブル事例を踏まえて、自分の言葉で説明できるようにする
この資格試験は「難易度が高い試験問題を解く力」よりも、「現場で必要な知識をきちんと理解しているか」が問われるのが特徴です。
合格率と難易度の実態
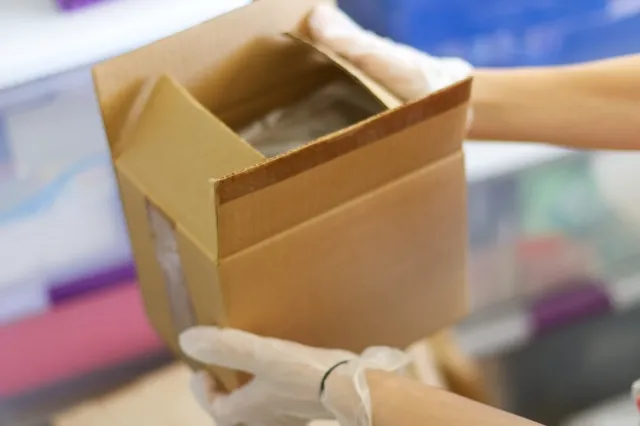
遺品整理士資格の合格率は約65%前後とされており、数字だけを見ると比較的高い水準です。これは「誰でも簡単に受かる」という意味ではなく、あくまでテキストに沿って真面目に学習した人が多いため、この数値になっています。
難易度のポイントは以下の通りです。
- 記述式中心の課題
テキストを参考にできるとはいえ、自分の言葉でまとめる必要があるため、丸暗記だけでは不十分です。 - 法律や専門用語への理解
廃棄物処理法や古物営業法など、慣れない法律用語を理解し、適切に文章に反映させる必要があります。 - 現場経験があると有利
未経験者でも合格可能ですが、現場経験者は具体例を交えて回答できるため有利です。 - 通信教育の自己管理能力
2か月程度の学習期間が設定されており、期限内に課題を提出する計画性が求められます(レポート提出期間の延長申請も無料で可能)。
総合的に見ると、遺品整理士資格は努力すれば十分に取得可能な難易度です。特に、受験者の多くは業務に直結する目的で挑戦するため、学習意欲が高く、高い合格率につながっています。
学習期間と効率的な勉強法

遺品整理士資格の標準的な学習期間は約2か月とされています。通信講座で送られてくる公式テキストと課題をこなす形式が一般的で、自分のペースで進められる一方、自己管理が重要です。
効率的な勉強法のポイントは以下の通りです。
- まず全体像を把握する
テキストを最初から順に読むよりも、まずは目次を見て全体の流れを理解しましょう。全体像を掴むことで、重要箇所の優先度が見えてきます。 - 法律・制度部分は繰り返し復習
廃棄物処理法や古物営業法など、専門用語が多い箇所は理解が追いつきにくいため、何度も読み返し、簡単なメモを作成すると定着が早まります。 - 記述式課題の練習
合格には論理的な回答力が必須です。模範解答をなぞるのではなく、自分の言葉で説明できるように練習しましょう。特に事例問題では具体例を交えて記述すると評価が高くなります。 - 週単位のスケジュール管理
「週に〇ページ進める」「〇日までに課題提出」といった短期目標を設定すると、計画的に進められます。
総じて、遺品整理士資格は2か月の計画的学習で十分合格可能です。忙しい人でも、1日30分〜1時間の学習を継続することで無理なくクリアできます。また資格取得に必要なレポート提出期間も、無料で延長の申請をすることができます。どうしても期間に間に合わないようであれば、忘れずに延長の連絡をしてください。
資格取得にかかる費用と更新制度

遺品整理士資格の取得には、入会金と会費がかかります。金額は全国的に統一されており、入会金30,000円と会費8,000円(1年間有効)の合計38,000円が必要です。この費用には、公式テキスト・資料・DVD・問題集・合格証書などが含まれています。
また、遺品整理士資格は1年ごとの更新があります。会費の8,000円が必要になります。
費用面だけを見れば高額に感じるかもしれませんが、資格取得後は顧客からの信頼度が上がり、依頼単価の向上や営業面での強みになります。特に自治体や福祉関連の紹介案件では、資格の有無が受注可否に影響することもあります。
つまり、費用は資格を活かした業務展開で十分に回収可能であり、長期的な収益向上を狙える投資といえます。
合格後に得られるメリットと活用方法

遺品整理士の資格を取得すると、まず顧客からの信頼性が向上します。遺品整理は、遺族の思い出や故人の大切な品を扱うため、依頼者は安心して任せられる業者を求めています。資格を保有していることは、専門知識・倫理観・法令順守の姿勢を示す強力な証明となります。
また、自治体や福祉施設との取引にも有利です。多くの自治体では、遺品整理士資格を持つ業者を推奨リストに載せるケースがあり、行政からの案件受注や紹介につながります。さらに、孤独死や特殊清掃案件など、専門性の高い仕事を受けられるようになり、業務の幅が広がります。
営業面では、ホームページや名刺に資格を記載することで、競合との差別化が可能です。特に相続や不動産売却、福祉分野と連携したワンストップサービスを提供する場合、資格保有は大きな強みとなります。
つまり、この資格は単なる肩書きではなく、受注率アップ・単価向上・業務領域拡大といった直接的な利益に直結する実践的な武器になります。
資格取得が必要なケースと不要なケース

遺品整理士資格は必須ではありませんが、状況によっては取得が強く推奨されます。必要なケースとしては、自治体や福祉団体との提携を考えている場合、孤独死・特殊清掃など法的規制や専門知識が求められる現場に関わる場合が挙げられます。特に行政からの紹介案件や補助金制度を活用する場合、資格保有が条件となるケースが少なくありません。
また、新規参入や競合との差別化を図るためには、資格が大きな信頼材料となります。遺品整理業界は参入障壁が低い一方で、依頼者の不安感が大きい分、資格を持つことで安心感を与えられます。
一方、不要なケースとしては、不用品回収やリサイクル業務がメインで、遺族対応や法的手続きに深く関わらない場合です。例えば、一般的な家具や家電の引き取りを中心に行う事業者であれば、資格がなくても業務は可能です。ただし、その場合も遺品整理を看板に掲げるなら資格を取得しておくほうが無難です。
結論として、遺品整理を本格的に事業化し、信頼性や案件の幅を広げたいなら、資格取得は長期的な投資価値が高いといえます。
記事全体のまとめ

遺品整理士資格は、遺品整理業務における専門知識と倫理観を身につけるための民間資格です。合格率は約65%と比較的高く、学習内容も初心者向けに構成されています。そのため「難易度は決して高くない」が、単なる丸暗記ではなく、法令・マナー・実務の理解が求められます。
資格取得のメリットは、顧客や自治体からの信頼度向上、業務の差別化、そして廃棄物処理や相続関連案件での強みです。取得方法は通信講座で、2か月程度で修了可能。受講料は38,000円で、学習の負担は比較的軽いため、現職のままでも取得が目指せます。
ただし、資格取得はあくまでスタート地点であり、実務経験や信頼構築こそが成功の鍵です。資格を取って終わりではなく、現場経験や法改正への対応を継続することで、長期的に選ばれる遺品整理業者となることができます。