相続では、被相続人が残した「借金」も、預貯金や不動産と同じく相続財産として扱われます。しかし、債務のある遺産相続は必ずしも承継する必要はなく、選択によって対応できるため、正しい知識を持つことが安心につながります。
相続で「債務」はどうなる?基本的な承継ルールと選択肢

相続において、被相続人の債務は相続財産として扱われます。つまり、借金は遺産相続として、預貯金や不動産と同様に承継の対象になります
ただし、相続人には債務を引き継ぐかどうかを選ぶ権利があります。主な選択肢は以下の通りです。
- 単純承認:プラスもマイナスもすべて引き継ぐ方式。
- 限定承認:プラスの財産の範囲内で債務を引き受ける方法。
- 相続放棄:最初から相続人とならない選択。借金も引き継ぎません。
いずれも手続きに期限(通常は相続開始を知ってから3ヶ月)や要件があり、特に限定承認は家庭裁判所への申述が必要です。
つまり、債務のある相続は選べる問題であり、適切な手続きをとれば安心して対応できます。本記事では、それぞれの仕組みと選び方を丁寧に解説していきます。
「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の違いと選び方

相続債務への対応は、3つの方法から選択できます。それぞれメリット・デメリットが異なるため、状況に応じた判断が重要です。
- 単純承認
プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぎます。被相続人が残した債務が少額で、財産が十分にある場合に有効です。ただし、一度単純承認すると債務返済の義務も免れません。 - 限定承認
相続したプラスの財産の範囲内で債務を引き受ける方法です。例えば財産が1,000万円で債務が1,500万円の場合、1,000万円の範囲までしか返済義務が生じません。借金額が不明な場合に安全策として有効ですが、家庭裁判所への申述や債権者への公告など手続きが複雑です。 - 相続放棄
最初から相続人とならない選択肢です。債務は一切引き継がず、返済義務もありません。多額の借金が判明している場合や、財産より債務が大きい場合に有効です。相続放棄も家庭裁判所への申述が必要で、期限は相続開始から3ヶ月以内です。
この3つの方法は一度選択すると原則として変更できないため、相続債務の正確な調査が重要です。特に、被相続人の通帳、郵便物、借入契約書、保証人契約の有無などを徹底的に確認しましょう。
債務は「当然に分割される」可分債務とは?

相続で承継される債務のうち、多くは可分債務に該当します。可分債務とは、法定相続分に応じて相続人ごとに分割して負担することができる債務のことです。
例えば、被相続人が銀行から300万円の借入をしていた場合、相続人が2人で法定相続分が1/2ずつであれば、それぞれ150万円ずつ返済義務を負います。この場合、債権者は一部の相続人に全額を請求することはできません。必ず各相続人の負担分のみを請求することになります。
ただし、可分債務はあくまで債務の性質上分割可能な場合に限られます。例えば、金銭債務や物品の引き渡し義務などは可分債務に該当しますが、保証債務や連帯債務などは不可分債務に該当し、分割できません。
注意すべきなのは、相続人同士で「債務は〇〇が全額負担する」と取り決めても、債権者にはその取り決めを主張できない点です。債権者は法定相続分に基づいて請求してくるため、内輪の合意はあくまで相続人間の問題として処理されます。
相続債務が可分債務かどうかを判断するには、契約書や債務の内容を確認し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することが重要です。間違った判断をすると、思わぬ債務負担が生じる可能性があります。
分割のできない「不可分債務」「連帯債務」「保証債務」の違い

相続で引き継ぐ債務の中には、相続人の間で分割できないものがあります。代表的なのが不可分債務、連帯債務、そして保証債務です。それぞれの特徴と注意点を理解しておくことが大切です。
- 不可分債務
債務の性質上、物理的に分割できない債務です。例えば、不動産の引き渡しや特定の物品の返還義務などは、一部だけ履行しても債務全体が消えることはありません。この場合、相続人全員が債務全体の履行義務を負います。 - 連帯債務
契約によって定められることが多く、各相続人が債務全額の返済義務を負います。債権者は相続人のうち誰に対しても全額請求でき、1人が全額支払えば他の相続人の義務も消滅します。住宅ローンや事業資金の借入契約などで見られます。 - 保証債務
被相続人が他人の借金の保証人になっていた場合、その保証債務も相続されます。保証債務は連帯保証が付いている場合が多く、こちらも全額の返済義務を負う可能性があります。特に注意が必要なのは、保証債務の存在が被相続人の死後に発覚するケースです。この場合、相続放棄や限定承認の期限内に見つけなければ、意図せず高額の負債を背負うことになります。
これらの債務は、相続人の人数に関係なく全員が全額の返済義務を負うという重大な特徴があります。相続開始後は、契約書や借入明細、登記簿などを確認し、早急に債務の種類を把握することが重要です。
相続債務の調査方法と確認すべきポイント
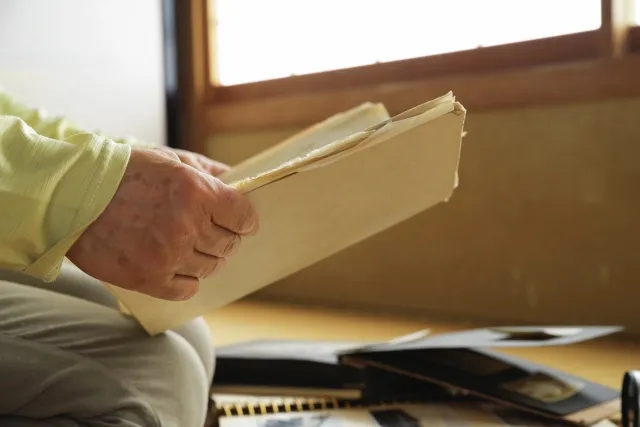
相続が発生したら、まず最初に行うべきことの一つが債務の全容把握です。借金や保証債務は表面化していないケースも多く、早期発見がその後の判断を大きく左右します。以下は、相続債務を調べる際の主な方法と注意点です。
- 通帳・取引明細の確認
被相続人の銀行口座を確認し、不自然な入出金や定期的な引き落としがないかをチェックします。特に消費者金融やカードローンの返済履歴があれば債務がある可能性が高いです。 - 郵便物の確認
金融機関やカード会社からの請求書、督促状、契約更新のお知らせなどは債務の存在を示す手がかりになります。 - 信用情報機関への照会
全国銀行個人信用情報センター(KSC)、CIC、JICCなどの信用情報機関に開示請求を行うことで、ローンやクレジット契約、延滞履歴などを確認できます。相続人であれば、必要書類を提出して照会可能です。 - 不動産登記簿の確認
不動産に抵当権や根抵当権が設定されていれば、住宅ローンや事業資金の借入が残っている可能性があります。 - 保証契約の有無を確認
被相続人が他人の借金の保証人になっていた場合、その契約書が残っていないか探します。保証債務は相続後に発覚すると対応が難しくなるため要注意です。
ポイントは、相続放棄や限定承認の期限(相続開始を知ってから3か月以内)に間に合うよう、スピーディに調査を行うことです。債務の有無や金額を把握すれば、相続を「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のどれにするか、冷静に判断できます。
相続放棄と限定承認の違いと活用法

相続で債務が判明した場合、相続人には相続放棄と限定承認という2つの大きな選択肢があります。どちらを選ぶかによって、今後の負担や財産の取り扱いが大きく変わります。
相続放棄
- 概要:相続放棄は、被相続人の財産も債務も一切受け継がない手続きです。
- メリット:借金や保証債務から完全に解放される。
- デメリット:プラスの財産(不動産・預金など)も一切相続できない。
- 期限:相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
限定承認
- 概要:相続財産の範囲内で債務を返済し、残りがあれば相続する方法です。
- メリット:プラスの財産が残れば受け取れる。
- デメリット:相続人全員の合意が必要で、手続きや清算が複雑。
- 期限:こちらも相続開始を知ってから3か月以内。
活用のポイント
- 債務額が不明な場合や、プラスの財産が大きい可能性がある場合は限定承認が有効です。
- 逆に、明らかに債務超過でプラスの財産がない場合は相続放棄が安全です。
- 限定承認は不動産や事業資産を守りつつ、債務整理ができるため、家業や店舗を継ぐケースで活用されることもあります。
相続放棄も限定承認も、期限を過ぎると単純承認(すべてを相続)したとみなされるため、債務調査と並行して早急な判断が必要です。
相続放棄や限定承認の手続きの流れ

債務が判明し、相続放棄や限定承認を選択する場合は、家庭裁判所での正式な手続きが必要です。期限は「相続があったことを知った日から3か月以内」です。この期限内に動けるかどうかが成否を分けます。
- 相続放棄申述書または限定承認申述書(家庭裁判所の窓口またはWebサイトで入手可能)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 申述人(相続人)の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票や附票
- 手数料用の収入印紙、郵便切手
相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出します。相続放棄は1人ずつ手続きできますが、限定承認は相続人全員の共同申述が必要です。
書類の不備や内容確認のため、家庭裁判所から照会書が届く場合があります。回答は期限内に行わなければなりません。
- 相続放棄の場合:確定後、第三者に対して債務を負わない旨を主張できます。
- 限定承認の場合:相続財産の清算手続きに入り、債権者への公告・弁済が行われます。
注意点
- 期限を過ぎると手続き不可となり、借金も含めてすべてを相続することになります。
- 相続放棄後でも、相続財産を処分すると「単純承認」とみなされる恐れがあるため注意が必要です。
- 限定承認は手続きが複雑で期間も長くかかるため、弁護士への依頼が望ましいケースが多いです。
保証債務や連帯保証がある場合の注意点

相続における債務は、被相続人が直接借りたお金だけではありません。保証債務や連帯保証も相続の対象となり、相続人がその責任を引き継ぐことになります。これを見落とすと、思わぬ高額な請求が後から届くこともあります。
保証債務の特徴
- 被相続人が他人の借金の保証人になっていた場合、その債務は相続人にも引き継がれます。
- 保証債務は「将来発生する可能性がある債務」も含まれるため、現時点で請求がなくても後日発生することがあります。
連帯保証のリスク
- 連帯保証人は、主たる債務者と同じ責任を負うため、債権者は主たる債務者に請求する前に相続人に直接請求できます。
- 返済額が高額になりやすく、資産より負債が大きくなるケースも少なくありません。
対処法
- 相続発生後、被相続人が保証人になっていなかったかを調査することが重要です。
- 信用情報機関(CIC、JICCなど)の照会
- 金融機関や知人への聞き取り
- 契約書類の確認
- 保証債務や連帯保証があることが判明したら、相続放棄または限定承認を検討します。
- 不動産や預金などのプラス財産よりも負債額が多ければ、相続放棄が現実的な選択です。
注意点
保証債務は、債務額が未確定でも相続の対象になるため、油断すると数年後に突然請求される可能性があります。特に事業関係や親族間の保証契約は見落としやすいため、早期の確認が必須です。
相続債務の調査方法と確認ポイント
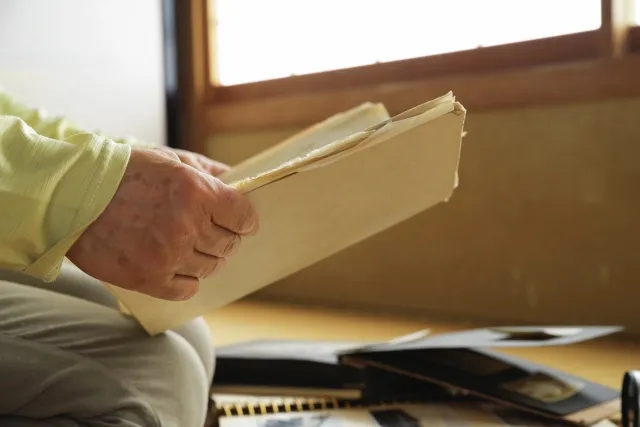
相続で最も避けたいのは、知らないうちに借金を引き継いでしまうことです。そのためには、被相続人の債務状況を正確に把握することが重要です。以下では、具体的な調査方法と確認すべきポイントを解説します。
① 金融機関への照会
- 被相続人が利用していた銀行や信用金庫に問い合わせ、ローンや借入の有無を確認します。
- 特に住宅ローン、マイカーローン、カードローンなどは残高証明書を取得すると確実です。
② 信用情報機関での調査
- CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターなどに情報開示請求を行うことで、クレジット契約や借入状況がわかります。
- 請求には戸籍謄本や相続関係を示す書類が必要です。
③ 契約書・請求書・郵便物の確認
- 自宅や事務所に保管されている契約書、保証契約、借用書、督促状などをチェックします。
- 金融機関やカード会社から届く郵便物も重要な手掛かりになります。
④ 保証債務・連帯保証の確認
- 知人や親族間の保証契約は書面が残っていない場合もあるため、周囲への聞き取り調査も必要です。
⑤ 税金や公共料金の未払い調査
- 固定資産税、自動車税、健康保険料などの滞納も相続債務に含まれます。役所での照会が有効です。
調査のポイント
- 相続開始後は、3か月以内の熟慮期間内に全ての債務を把握する必要があります。
- 少しでも不明点があれば、期限内に相続放棄や限定承認の手続きを仮で行い、その後詳細調査を進める方法もあります。
相続債務の支払い方法と優先順位

相続が発生すると、被相続人の財産はプラスの資産だけでなくマイナスの債務も引き継がれます。債務をどのように支払うか、またどの債務から優先的に処理すべきかを理解することは、相続人にとって非常に重要です。
支払い方法
- 相続財産から支払う
- 預貯金、不動産売却代金、有価証券などを現金化して返済します。
- 自己資金から支払う
- 相続財産だけでは不足する場合、相続人が自己資金を充てることになります。
- 任意整理・分割返済
- 債権者と交渉して返済計画を見直すことも可能です。
- 相続放棄・限定承認
- プラス財産より債務が多い場合は、相続放棄や限定承認により負担を回避できます。
優先順位
債務の支払いには、法律上の優先順位があります。
- 葬儀費用・相続手続きに必要な費用(ただし、葬儀費用は法定優先順位外ですが実務上優先されることが多い)
- 税金・社会保険料の滞納分
国税(所得税・相続税など)、地方税(固定資産税・住民税など)は他の債務より優先して支払う必要があります。 - 担保付き債務
住宅ローンなど抵当権が設定されているものは、担保物件を売却して返済します。 - 無担保債務
カードローン、消費者金融、保証債務などがこれにあたります。
注意点
- 優先順位を無視して返済すると、後から差し戻しや二重返済のリスクが発生します。
- 特に税金の滞納は延滞税や差押えのリスクが高く、早期対応が必要です。
- 分割協議や財産分割前に、債務処理の方針を家族で統一しておくことが重要です。
まとめ:相続債務は早期把握と的確な判断がカギ

相続において債務(借金や未払い費用)は、プラスの財産と同じく相続の対象となります。放置すると、知らぬ間に多額の負債を背負い込むリスクがあり、相続人の生活に大きな影響を与えかねません。
そのため重要なのは、相続開始直後の迅速な債務調査と3か月以内の判断です。金融機関照会や信用情報開示、契約書類の確認などを通じて、被相続人の負債を漏れなく洗い出しましょう。
債務が多い場合は、相続放棄や限定承認で負担を回避できますし、プラス財産がある場合も債務の支払い順序や方法を誤らないことが大切です。特に税金や社会保険料は優先度が高く、早期対応が必要です。
相続債務の問題は、法的知識と実務経験が求められるケースが多くあります。少しでも不明点や不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に早めに相談することが最善のリスク回避策です。
正しい手順と判断で、相続による負の連鎖を防ぎ、安心して次の世代へ財産を引き継ぎましょう。